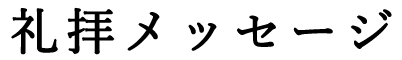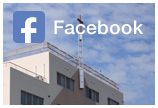顧みてくださる主
詩篇40:1-17
16世紀にスイスで宗教改革を起こしたジョン・カルヴァンは、詩篇には人間のあらゆる感情が鏡のように映し出されている、と言ったという。確かに、詩篇を読むと、人が心に溢れさせる、悲しみ、恐れ、望み、心配、思い煩いが随所に描かれている。だが、私たちが詩篇を読むとき、ただその描き出された感情に同調したり、浸ったりする程度に終わってはならない。なぜなら、神が、詩篇を私たちに与えた目的は、私たちが救いの完成に至り、信仰の高嶺を歩み、霊を成長させていただくところにあるからだ。今日開かれている詩篇40篇にも、詩人の感情が溢れんばかりに描かれているが、私たちはここに救い、信仰、霊の成長というポイントを見出す必要がある。
まず1-3節を見たい。ここに、神の真実と憐れみを賛美する者の姿を見ることができる。これは、この詩篇全体の総括だと言える。主を待ち望み、主に助けを求める声を聞いていただいて助け出された詩人が、歩みを確かにしていただき、神への賛美をもって周囲の者に主を証ししているのだ。では、どうすれば、そのような者となることができるのか。それが後に続く内容だ。
続く4節の「幸いなことよ」は、詩篇に多く見られる表現だ。真の幸いとは何か。罪の問題の解決だ(詩1:1,32:1,2)。「高ぶる者」や「偽りに傾く者」とは、私たちを罪に封じ込め、神の方を向かせない存在、サタンのことだと読める。私たちは、罪のために神から遠く離れ、サタンの手中に落ちたまま滅びる者だった。そんな私たちが滅びるのを惜しまれた神は、私たちを救うために、ひとり子キリストを遣わしてくださった。キリストが十字架にかかって死に、死を破ってよみがえられたことによって、私たちに救いの道が開かれた。どんな罪を犯した者であっても、自分の罪を悔い改め、キリストを救い主と信じるなら、罪の赦しと滅びからの救いをいただくことができる。神に背を向け、サタンの方を向いていた生き方から、もうサタンの方は向かないと方向転換し、神の方を向いて生きていくこと。これが、キリストの救いをいただいた者の生き方だ(マタ18:2,3)。
しかし、12節の辺りからトーンが一変する。明らかに、詩人は悩み、もがいている。何に悩み、もがいているのか。「わざわい」とあるが、原語では”悪”となっている。何か災難やトラブルではなく、自らの心に潜む性質のことだ。だから、「私の咎」と表現し、「私の心も私を見捨て」るほどの有様にまでなっているのだ。パウロもまた、同じ嘆きをあげている(ロマ7:15-24)。「私のうちに住んでいる罪」と繰り返し、神に逆らい、神が喜ばれない悪を内に宿し続けている肉の姿に苦悩している。詩人やパウロのように、私たちも、救われた後もなお残る罪の根に目を向け、自らの姿に絶望し、砕かれて神の前に出ていくなら、神は必ず私たちを導き、十字架を示してくださる。示された十字架に、私たちが自らの肉をつけて始末するとき、キリストが我が内に臨み、生きて働いてくださる(ガラ5:24, 2:19b,20a)。私たちは内に生きて働いてくださるキリストを通して、神に喜ばれる歩みを送ることができる。かつては、自分の思い、自分の考え、自分の都合で生きていたが、神の御心を知り、神の御心を行い、自らの姿を通して神の義を証しする者となる(8-10節)。
詩篇40篇は、神の顧みへの期待で締めくくられている(17節)。神の顧みは、ただ気にかけてくれるとか、心配してくれるといった程度のことではない。私たちの内側に光を当て、何が潜んでいるのかを明らかにし、私たちを正しく導くために必要なところを通らせ、そして、必要なら打って砕き、私たちを整えてくださることだ(詩143:7-12)。
私たちも神の顧みを求め、神の前に出ていきたい。私たちが砕かれて出ていくなら、神は必ず私たちを顧み、私たちに救いを与え、幸いを与え、正しく生きる道を与えてくださる。