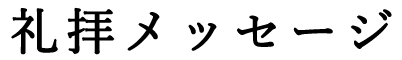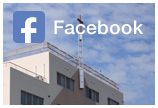夜ふけて日近づきぬ
ローマ13:11-14
本章にクリスチャンの日常的生活のあり方が述べられているが、1~10節には愛についての記述だ。しかし自らの内に、主に対しても隣人に対しても、愛していない現実がある。表面上は愛に富んだ人のように振る舞っても、腹の内は愛せない、赦せない、受け入れられないというものがある。
律法の要求(8,10節)とはなにか。それは、「心を尽くし、いのちを尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛」すること、また「あなたの隣人を自分自身のように愛」することだ(マタ22:37-40)。“神を愛せよ、隣人を愛せよ。”という律法の要求に、我らは応えられているだろうか。否、我らは律法の要求に応えていない。応えられないのだ。
しかし神は我らに、律法に応え得る者となる道を、キリストの十字架によって開き給うた。
それを知るためには、まず11節以下を学ばねばならない。「このように」(新改訳第3版)、「この事を」(口語訳)とは、心を尽くして主を愛し、主の愛で人を愛するわざのことだ。
今は、贖われた我らが眠りからさめるべき時だ。終わりの日の我らの救いの時が間近な時だ(1テサ5:8,9)。我らが主と同じ姿に変えられ、御前に立たせられる栄化の恵みが今にも与えられようとしている。この日は初め信じた時よりも、もっと近づいている。
「夜ふけて日近づきぬ」(12節a文語訳)。夜は更けて行く。闇はどんどん濃くなる。時代は悪化の一途をたどっている。まさに終末の様相だ。しかし、確実に昼(朝)が近づいている。主の再臨は近い。だから、闇の業を打ち捨てて、光の武具を身につけるべきだ。
闇の業とは、「遊興や泥酔、淫乱や好色、争いやねたみの生活」(13節)だ。ローマのクリスチャンたちはこれらの誘惑に囲まれていた。すべて自分の肉の欲を満たすものであり、少しも主の栄光にはならない。
4世紀の神学者アウグスティヌスは、当時の通俗的カトリックに不満を抱き、マニ教に傾倒したが、それにも行き詰まり、堕落して放蕩三昧の生活を送る中、敬虔な母モニカの祈りもあって、ロマ書と出会い、この13章12,13節に目が開かれて悔い改めた。
今、自分の心は何によって占有されているか。何に心が向いているか。実現させたい自分の願いや計画に向いているか、それとも主への愛と主の御心に対する従順で占められているか。再臨の近い今、主の前に自分がどういう魂であるかを省みたい。
光の武具を着けよう。キリストを着よう。闇の衣の上、肉の衣の上からはキリストを着ることはできない。古いものを脱がなけれならない(コロ3:9b,10)。古い人とは、救われたのになお自己中心な己、愛せない、赦せない、喜ぶ者と共に喜べない妬み深い自我のことだ。この古い人を捨て、新しい人、復活のキリストを着たい。
どこで古き人を脱ぎ捨てられるのか。キリストの十字架の上だ。キリストが死なれた十字架で己も共に死に、キリストが復活されたように私も魂がよみがえらされ、復活のキリストのいのちで生きるのだ。十字架による古き人の破壊と、聖霊による新しき人の建設だ。この転機がどうしても必要だ。ここを通ることなしには、心安らかに主の日を迎えることができない。
不信仰にならず、世と妥協せず、いつ主人が帰ってきても、備えのできている目を覚ましている僕になりたい(ルカ12:37)。そして、時を弁えて、魂に重荷をもって御言葉を宣べ伝えよう(2テモ4:2)。