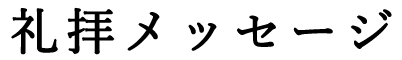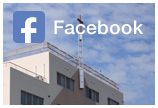ペヌエルの神
創世記32:22-32
本書に多くの人物が登場するが、ヤコブほど波乱万丈の生涯を送った人はいない。誕生から尋常ではなかった(25章)。イサクの妻リベカから双子の弟として生まれたが、兄エサウのかかとを掴んで出てきた。そこから“押し退ける者”という意味のヤコブと名づけられた。
彼は、抜け目のない才覚を持ち、兄から長子の特権を奪い、さらに父の祝福を横取りした(27章)。これによって彼は兄の憎しみを買い、叔父ラバンのもとへ逃れた。その途中、彼はベテルの体験をする(28章)。彼は神の実在を知った。それまで知らなかったことが自分の罪だと分かった。これが彼の救いの体験だった(28:16,17)。
彼は新しい出発をした。しかし、まだ逃亡は続ける。兄への恐怖はなくならない。肉だからだ。救われても肉の性質が残っているからだ。それが本章で始末される。
彼はマハナイムの神を知った(1,2節)。神の約束(31:3)を得て、兄のもとへ帰ろうと思い立った。信じて行けばよかったのだが、兄の恨みの深さを思うと不安だった。犯した罪は神の前には赦されたが、人の前に未精算だった。しかし、そんな彼に天使たちが現れた。神の陣営だった。救われた者を神は御使いをもって守り給う(詩34:7)。
彼は、模範的な祈りを捧げる(9-12節)。それは、①約束に立った祈り(9節)、②謙った祈り(10節)、③感謝の祈り(同)、④救いを求める祈り(11節)、⑤再び約束に立った祈り(12節)だった。しかし表面的な、言葉だけの祈り、上手で聞かせる祈りに過ぎなかった。
そのことは後の彼の行動で分かる(13-21節)。彼は兄への贈り物を3つに分けた。それは自分の身を守るための必死の肉策だった。神に委ねず、自分の我策肉策によって危機を乗り越えようとしたのだ。マハナイムの経験も、模範的な祈りも、自分のものになっていなかった。いざという時に古い自分、自我が台頭する。肉の性質そのものだ。
そんな彼にも、ついに神の取り扱いのメスが入る。神に取り扱われ、探られ、試みられても、なかなか最後の底板が砕かれないヤコブだったが、神は彼を見放さず、ヤボクの渡しで一人に追いやられた。家畜や奴隷はすでに贈り物として先に遣わしていた(22,23節)。家族の安全のためではなく、自分の安全のためだ(24節)。家族を犠牲にしてでも自分を守りたかった。自分が一番かわいかったのだ。
しかし、一人になったのは幸いだった。神の取り扱いのときだった。一人の人が格闘を挑んだ(24節)。頑ななヤコブに、神が直接干渉されたのだ。
神の使いに格闘を挑まれても、負けないヤコブの頑迷さだ(25節)。彼は、ついにもものつがいがはずされた。腰骨が砕かれたのだ。彼は格闘する相手が主ご自身だと分かって、食い下がって祝福を求めた(26節)。簡単には諦めない。いただくまで求め続ける。これは祝福を得る秘訣の一つだ。
彼は名を尋ねられて、「ヤコブです」と答えた(27節)。“押し退ける者です”と自分の性質を告白したのだ。自分がどれほど人と神を押し退けてきたかを知り、“こんな者です”と御前に出たのだ。
新約の光で見れば、これは、自我をキリストと共に十字架につけたことを意味する。そんな彼に「イスラエル(神の皇太子の意)」という新しい名が与えられた(28節)。これは、彼がキリスト内住の恵みを得たことを表す。魂の新創造だ。彼はその地を「ペヌエル(神の顔の意)」と名づけた(30節)。顔と顔を合わせて神を見たからだ。
夜が明け(31節)、陽は高く上った。いつもと同じ太陽だが、彼にとっては今までとは全く異なる太陽だった。彼の魂の暁(あかつき)だ。足の不自由は治らない。しかしそれが恵みのしるしだった。
こうして押し退ける者は、神の皇太子に造り変えられた。自我は砕かれ、もはや自分には頼らない、主にのみ信頼し、主からも信任される者になった(2コリ5:17)。
我らの神はペヌエルの神だ。我らの腰骨(自我)を砕き、根底から新しく創造し給う神だ。我らもペヌエルの体験をしたい。激しい渇きをもって、食い下がって求めよう。