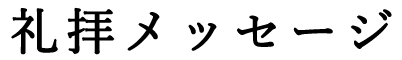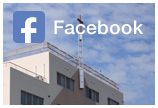心はうちに燃えていたではないか
ルカ24:13-35
イースターは、主の復活が我らにどれほど大きな希望をもたらしたかを思う時だ。
イエスが復活された日の夕方、二人の弟子たちがエマオに向かっていた。彼らは歩きながら、朝の出来事について論じ合っていた。そこへイエスが、一人の旅人のようにして彼らに加わられた。しかし彼らには、不信仰のため目がさえぎられて、主であることがわからなかった。彼らは、墓から帰った女たちの報告を「たわごと」(11節)としか思えなかった。不信仰は主の姿を見えなくする。
主は“何のことか、どんな事か”と尋ねられた。主があえて質問されたのは、彼らの信仰を見ようとされたのだ。彼らの反応は、①軽蔑だった。「あなただけが知らなかったのですか」(18節)という反問は傲慢に通じる。②不信仰だった。「力のある預言者でした」(19節)、「この方こそイスラエルを贖ってくださるはずだ、と望みをかけていました」(21節)、「また仲間の女たちが私たちを驚かせました」(22節)などの言葉から、イエスに対する彼らの認識の低さがうかがえる。彼らは結局イエスをその程度にしか見ていなかったのだ。
イエスは「ああ、愚かな人たち。…心の鈍い人たち」(25節)と嘆かれ、旧約聖書全体を諄々と解き明かされた。彼らは感動したが、まだイエスだとはわからない。
わかったのは、エマオ近くの宿での食卓で、パンを裂かれる姿を見たときだった(30,31節)。閉ざされていた彼らの目がようやく開かれ、懐かしいイエスの姿がわかった。ここに主の忍耐強い働きかけがあったのだ。
ペンテコステの日にペテロは、詩篇16篇8節から引用して、「私はいつも、自分の目の前に主を見ていた」(使徒2:25)と言った。見たから居てくださるのではない、居てくださるから見るのだ。これが信仰だ。
彼らは、「道々お話しになっている間も、聖書を説明してくださった間も…」(32節)と語り合った。聖書の御言葉が解き明かされる時、心が内に燃える。神の御言葉は、我らの心を燃やす。どのような炎で燃やすか。
①信仰の炎で燃やす。十字架と復活の福音に対する信仰だ。御言葉を聞かなければ、信仰の炎はない(ロマ10:17)。まず聞くことだ。それも、自分の魂に語られていると聞くのだ。自分の魂に当てはめて、謙虚に“自分はどうか”と問いつつ聞くのだ。
そして聞いたら信じるのだ。私を救い、潔め給う主を信じるのだ。すでに完成されている十字架の全き贖いを信じるのだ。信じようという熱い思いが与えられるはずだ。信仰の炎が燃やされるはずだ。
②愛の炎で燃やす。主を愛し、人を愛する愛だ。私をそこまで愛し給うた主の愛を知れば、私も主を愛したいと思う。冷たい心ではない、主への熱い愛が沸き起こってくる。我を愛し、わが為に己が身を献げ給いし主を、力の限り愛したいと思うはずだ。そして、そこから聖徒に対する、犠牲も惜しまない愛が与えられる。
「私たちの心は内に燃えていたではないか」という体験をしたい。信仰と愛の炎で燃やされたい。
復活の主は、再臨の主の予表でもある。再び来られる主を、信仰と愛をもって待ち望もう。