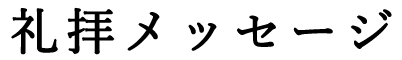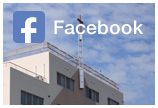キリストを生きる
ピリピ1:12-30
パウロがローマの獄中から、ピリピの教会の信徒に宛てて書いた獄中書簡だ。獄中という逆境にあったが、本書からは悲壮感は微塵も感じられない。むしろ、「喜ぶ」「喜び」という言葉が多用されている。彼が逆境にあってこの“喜びの使信”を送ることができたのはなぜか。
パウロはまず、自分の身に起こった投獄という出来事が、福音の前進に役立ったことを感謝している(12節)。それは、彼の投獄がキリストのゆえであることが兵営全体に知られ、証しになっているからであり(13節)、教会の信徒が、信仰によって今まで以上に大胆にみ言葉を宣べ伝えるようになったからであり(14節)、さらには、彼を妬む者たちが、党派心からであるにせよ、熱心にキリストを宣べ伝えるようになったからだ(15-18節)。
彼の願いは、「生きるにも死ぬにも私の身によって、キリストがあがめられること」(20節)だった。早く出獄して福音を広く伝えたいと願わなかったはずはない。しかし、最大の願いは、自分の身によってキリストの御名があがめられることで、そのためには死をも辞さないという思いだった。
「私にとっては、生きることはキリスト、死ぬことも益です」(21節)とは、パウロの本心だった。この言葉には違和感がある。“生きることは楽しい・苦しい”とは言うが、「生きることはキリスト」という言い方はしない。ここに深い意味がある。「生きることはキリスト」とは、どういうことか。これは、キリストが何のためにこの世に来られたかに深く関わる。
キリストは、永遠の初めからおられた神の独り子だったが(ヨハ1:1)、人となってこの世に来られた(同1:14)。罪のないお方だったが(1ペテ2:22)、十字架にかかって死なれた。それは、神に対して罪を犯し、滅びるばかりの我らを贖うための身代わりの死だった(同2:24)。罪を悔い改め、キリストの十字架を信じるなら、誰でも罪が赦され、滅びから免れさせられる。まず、この救いをいただきたい。
罪から救われた魂は、神に喜ばれるように生きたいと願う。ところが現実は、どこまでも自分を喜ばせたい己、み心が成るようにと祈りながら、実は自分の思い通りになることを願う自分、主に従いますと言いながら、自分の都合の良い範囲内とか、自分が損をしない程度にとか、勝手な条件をつけている。これが汚れた肉の姿だ。
汚れを抱えたままでは、聖いお方である神は決して喜ばれない。けれども、我らは自分で自分を聖くすることはできない。だからキリストが十字架にかかられた。自分の汚れた肉、古き人を意志と信仰もって十字架につけるなら(ガラ5:24)、キリストが内に臨まれる。そして、信仰によってキリストの命で生きる者となる(ガラ2:20)。
ここから「生きることはキリスト」という生き方が始まる。キリストが内に生き給う。私がキリストを生きるのだ。主がどこまでも自分を低くして、神のみ心だけに喜んで従われたように(詩40:8、ヨハ5:19)、私もそのように生きる者になるのだ。
「キリストの福音にふさわしく生活」(27節)する、すなわち、キリストの十字架と復活の福音にあずかった者らしく生きる生き方は、苦難が伴う道だろう。しかし、キリストのゆえの苦難、福音のゆえの苦しみなら、賜物として受けとめることができるのだ(29節)。なんと高尚なる生涯か。
パウロだからそのような生き方ができたと思ってはならない。我ら贖われた者すべてに可能な生き方であり、また主が我らに願っておられる生き方だ。キリストを生きる生涯を求めていこう。