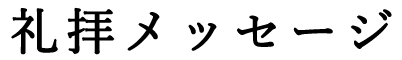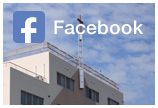大いなる救い
マルコ5:1-20
イエスは、ガリラヤ湖の向こう岸に渡り、デカポリス地方へ行かれた。そこは、ユダヤ人が嫌った異邦人であるゲラサ人の地で、また豚を飼う民の地だった。主がわざわざその地に足を踏み入れたのは、一人の悲惨な男を救うためだった。
彼の悲惨さが克明に描写されている(3-5節)。彼は墓場を住み家にし、鎖でつなぎ留められ、足かせまではめられ、昼夜絶え間なく叫び続け、石で自らを傷つけていた。全くの絶望状態だ。
彼をこれほど無惨にしていたのは、「汚れた霊」(2節)つまりサタンだった。イエスは彼を、このサタンの支配から解放された。彼は正気になって主の足もとに座っていた(15節)。彼は、闇から光へ、死から命へ、絶望から希望へ変えられたのだ。主のなされた大きな救いのみわざ、神の憐れみのみわざだった。
ここで覚えるべきことは、このゲラサ人は我らの姿だということだ。彼が墓場を住家にしていたように、我らは罪のために死と隣り合わせにいる。彼に足枷(あしかせ)がはめられたように、我らは罪の奴隷の状態だ。彼が叫び続けて人々とのコミュニケーションが取れなかったように、我らは神との交わりか断たれた者だ。彼が自傷行為にふけったように、我らの内の罪は、自らを、他人を、そして何よりも神の御心を傷つけるものだった。
主はそのような我らを愛し、憐れみ、大いなるみわざをなし給うた。主は十字架で血潮を流し、我らに血による贖い、すなわち罪の赦しを与え給うた(エペ1:7)。そして、赦罪のみならず義認の恵みを与え給うた(使徒13:38,39口語)。これは実に豊かな憐れみだ。こんな者が、何の功績もないのに、ただ神の恵みによって、一度も罪を犯さなかった者として認めてくださるのだから(ロマ3:24)。
この憐れみは、悔い改めと信仰をもって主の前に出ていった魂に向けられる。認罪-悔い改め-十字架信仰の手順に従って、素直に御前に出た魂を、神は限りなく憐れみ給う。
さらに神の憐れみは、魂の探みまで届く。救われた魂は、まだ神に喜ばれない古き人、自我に気づく。不信仰・不従順で、妬み深く、強情な肉の自分に愕然とする。ゲラサの村人らは、男が正気になって主の足もとに座っているのを、素直に喜ばず、主に立ち退きを要求した(17節)。自分たちの平和が壊されるから、財産が失われるからで、自分の幸福しか考えない自己中心の人間の姿だ。これこそ自我の醜い姿だ。
十字架の血は、そんな肉を全くきよめる。古き人が十字架でキリストと共に死んだ魂に、キリストが内住され、神の所有とされる(イザ43:1)。このような者がきよい者とされ、神のものとされるとは、なんと大いなる憐れみか。この憐れみは、やはり主の前に出ていった魂に与えられる。御言葉の光に照らされて自己の真相を認め、すでに成し遂げられている十字架のみわざを信じた魂を、神は憐れみ給う。神の憐れみは、我らに救いと聖潔(きよめ)の全き贖いを与えるのだ。
イエスは一人の魂を大切にされる。そのためなら、豚をも躊躇(ちゅうちょ)なく捨て給うた。主は、囲いから迷い出た一匹を探し続け給う。一人の魂が救われたら、そしてきよめられたら、天での喜びは大きい。
男は、イエスのお供を願い出た。神の憐れみをいただいて救われた魂なら当然だ。しかし、主はそれを許されず、家族のもとへ帰るよう言われた。彼の使命は家族への証しだった。主は、我らにも“親しき者に帰れ”と言われる。主の贖いのみわざを、主の豊かな憐れみを告げ知らせよと言われる。従いたい。